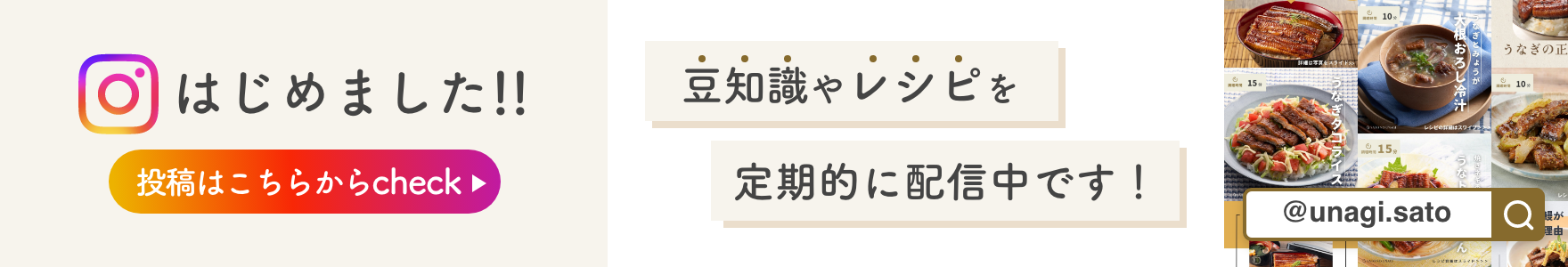うなぎの栄養を徹底分析!豊富な成分についてやおいしく楽しむアレンジレシピも紹介

ビタミンAやDHA・EPAをはじめとした多彩な成分が豊富に含まれ、免疫力や血管の健康をサポートしてくれるのが、うなぎの大きな特徴とされています。
エネルギー源となるたんぱく質やカルシウムなど、体の基礎を支える要素も充実しているため、栄養バランスを意識する方にとっては理想的な食材と言えるでしょう。まずはうなぎの優れた栄養価を確認しながら、より効果的に取り入れるコツを学んでいきましょう。

著者紹介
日本最大のうなぎの産地である鹿児島県から高品質なうなぎをお届けする「さとうの鰻」です。活きの良い鰻のみを厳選して美味しく焼き上げ、全国に発送しております。
今回は、うなぎの栄養について徹底解説していきます。ぜひこれを機会にうなぎの魅力について知って頂ければと思います。
うなぎに含まれる豊富な栄養素

うなぎは多種多様なビタミンやミネラル、不飽和脂肪酸をまとめて摂取できる貴重な食品です。特に疲労回復や免疫力強化に欠かせないビタミンB群や、骨を強く保つためのカルシウムといった栄養素が豊富に含まれています。これらの成分が相乗効果を発揮し、夏場の疲労対策にもぴったりといわれています。
さらに、抗酸化作用を持つビタミンEをはじめ、老化の原因である細胞の酸化を抑える要素も充実しています。ビタミンなどの美容面に役立つ栄養素も含まれているため、体だけでなく肌や粘膜のケアにも役立つのが大きな魅力です。
DHA・EPA:動脈硬化予防に期待
うなぎにはDHAやEPAといった不飽和脂肪酸が豊富に含まれています。これらの成分は血液をさらさらにし、動脈硬化や高血圧などのリスクを下げると考えられています。
現代人にとって不足しがちな栄養素でもあるため、うなぎを食卓に取り入れることで意識的に補給できる点が魅力です。(1)(2)
カルシウム:骨や歯を強化
カルシウムは骨や歯を構成するために欠かせないミネラルです。うなぎは比較的カルシウムを多く含み、ビタミンDとの相乗効果で効率的な吸収が期待できます。
成長期や骨粗しょう症対策など幅広い世代にとって大切な栄養素を、うなぎを通して手軽に摂取できるのは大きなメリットです。(3)(4)
ビタミンA:粘膜や目の健康を維持
ビタミンAは皮膚や粘膜の保護、視力維持などに大きく貢献します。
うなぎにはレチノールという形でしっかりと含まれているため、ドライアイや肌荒れ防止に役立つでしょう。特にパソコンやスマートフォンを多用する現代人にこそ、目かすみ対策として取り入れたい栄養素です。(5)(6)
ビタミンB群:疲労回復に役立つ
ビタミンB1やB2、B6などのビタミンB群は多くのエネルギー代謝に深く関わる大切な栄養素です。
夏場に感じやすい倦怠感や疲労回復をサポートしてくれるため、暑い季節にうなぎが好まれるのも納得できます。糖質の代謝にも関与するため、ご飯との相性も良いといえます。(7)(8)(9)
ビタミンE:抗酸化作用により老化を防ぐ
うなぎには、ビタミンEが豊富に含まれており、その強力な抗酸化作用によって細胞の酸化を抑制し、アンチエイジングにも役立ちます。
紫外線などでダメージを受けた肌のケアにも働きかけるため、美肌維持にも欠かせない成分です。栄養バランスに優れたうなぎを取り入れることで、内側からの美容と健康ケアが目指せます。(10)(11)
ビタミンD:カルシウム吸収を促進
ビタミンDはカルシウムやリンの吸収を促す役割があるため、骨や歯の健康に大きく寄与します。
日光に当たることで体内合成されますが、食事から補うのも重要です。うなぎを摂取することで、ビタミンDとカルシウムをまとめて摂り入れることが可能になります。(12)(13)
たんぱく質:筋肉や肌をつくる基礎
たんぱく質は筋肉や臓器、肌など体を構成するための基盤となる栄養素です。うなぎは良質なたんぱく質源として知られ、加齢による筋力低下や肌の衰えを予防したい方にもおすすめできます。
ビタミンやミネラルとの相互作用により、効率よく体の修復や形成をサポートします。(14)(15)
うなぎと梅干しの食べ合わせって悪いの?

古くから言い伝えられてきた「うなぎと梅干し」の食べ合わせが悪いという話には、はっきりとした科学的根拠はありません。むしろ梅干しに含まれるクエン酸が消化を助け、うなぎの脂っこさを和らげる面があるとされています。現代ではバランスよく食べることで栄養を取り入れやすくなるとの見解が一般的でしょう。
食事の組み合わせによる効能は諸説あり、個人差や体調にも大きく左右される部分があります。そのため一概に絶対NGとは言えず、むしろうなぎの脂が気になる際には梅干しの酸味がさっぱり感をもたらすことで食べやすくなるとの意見もあります。
食べ合わせが良いとされる理由
梅干しに多く含まれるクエン酸は胃の働きを助け、脂っこい料理を食べやすくする効果があります。うなぎのように脂質の多い食材でも、梅干しの酸味が加わることで味わいがさっぱりと感じられるでしょう。
誤解が広まった背景
昔は食材の保存状態や衛生面が今ほど整っておらず、食あたりの原因が梅干しと組み合わせたことに混同されて伝えられた可能性があります。酸味と脂の相性など、口当たりを重く感じる人もいたため「悪い組み合わせ」と噂になったとも考えられます。
現在では保存技術が進歩しているため、適切に調理すれば安心して楽しめるということも知っていただければと思います。
栄養価の高いうなぎをより美味しく楽しむアレンジレシピ

栄養たっぷりのうなぎを、より手軽に家庭で味わうアイデアレシピをご紹介します。
うなぎは蒲焼きだけでなく、素材の良さを活かしたアレンジ次第でさまざまな料理に応用できます。柳川風やちらし寿司など、旬の野菜やほかの食材と組み合わせることで栄養バランスもさらにアップします。調理方法の工夫次第で、塩分や糖質を必要以上に摂りすぎないように調整も可能です。
簡単な副菜や汁物を加えて栄養の偏りを抑えるのも、うなぎを美味しく取り入れるコツです。ビタミンCや食物繊維が豊富な野菜と合わせれば、身体にしっかりと栄養を届けながらさっぱり楽しめます。日常の食卓でも無理なく取り入れられるようなレシピが増えているため、ぜひ活用してみてください。
うなぎの柳川風アレンジ
ゴボウや玉ねぎなどの野菜と一緒に、うなぎを割り下で煮込み、溶き卵でとじるのが柳川風の定番スタイルです。
うなぎの旨味が溶け込んだダシとゴボウのほろ苦さが絶妙な組み合わせを生み出します。短時間調理でも栄養を損なわず、しっかりとした味付けでご飯との相性も抜群です。
菜の花とうなぎのちらし寿司
春の季節におすすめの一品で、菜の花のほろ苦さとうなぎの脂が見事に調和します。
酢飯にうなぎのかば焼きをのせ、彩りのよい錦糸卵や菜の花をあしらえば見た目にも華やかです。おもてなし料理やお祝いの席でも活躍し、栄養価も高いので満足感のあるメニューに仕上がります。
うなぎの栄養に関するよくある質問

うなぎについて、よく寄せられる疑問や気になる点をQ&A形式でまとめました。
うなぎは健康効果や美容効果が高い食材として広く認知されていますが、脂質が多くてカロリーが気になるという声も少なくありません。実際にはビタミンやミネラルが豊富で、上手に取り入れればむしろ体調を整える助けになります。ここでは、そんなうなぎにまつわる代表的な疑問点を解説していきます。
また、日々の食生活にどう組み込めばうなぎのポテンシャルを最大限に活かせるかも、多くの方が知りたいところです。調理方法や一緒に食べる食品など、小さな工夫で栄養価をさらに高めることが可能です。疑問や不安を解消し、メリットたっぷりのうなぎを楽しみましょう。
健康診断の結果や生活習慣病が気になる方には、摂取量や調味料の選び方が大きなポイントとなります。自分の体質や生活リズムに合わせて調整しましょう。
うなぎは体にいいの?
うなぎには免疫力の強化をサポートするビタミンAやビタミンEをはじめ、カルシウムやたんぱく質が豊富に含まれています。
体力増進や疲労回復にも役立つため、さまざまな年齢層にメリットがあるでしょう。塩分やカロリーの取りすぎに注意さえすれば、体に良い食材として取り入れやすい存在です。
なぜうなぎは栄養価が高いの?
うなぎにはDHAやEPAなどの不飽和脂肪酸からビタミンB群、ミネラル類までバランスよく含まれています。
タンパク質も豊富で、筋肉や臓器、肌の維持・修復に必要な成分がまんべんなく揃っている点が特徴です。多面的に高い栄養価を持つため、エネルギー源としても体作りのサポートとしても有効とされています。
疲労回復に効果的なのはなぜ?
うなぎに含まれるビタミンB群や良質なたんぱく質が、糖質や脂質の代謝を助け、エネルギー生産を効率化します。
さらにビタミンAやE、亜鉛などの栄養素が免疫システムに働きかけ、疲労からの回復をサポートしてくれるのです。夏バテ防止にも適した食材として、古くから愛され続けている理由がここにあります。
うなぎの豊富な栄養を効果的に取り入れよう

うなぎは健康や美容に嬉しい栄養素が多く含まれています。毎日の食生活に上手に活かしてみましょう。
うなぎはビタミンAやB群、D、Eなどのビタミン類とカルシウム、DHA・EPAといった多彩な栄養素を含む、非常にバランスの良い食材です。加えてたんぱく質など、美容と健康を同時にサポートする要素が豊富に詰まっています。定期的に食べることで、疲労回復や骨の強化など、日々の体調をしっかりサポートしてくれるでしょう。
調理方法や食べ合わせを工夫することで、カロリーや塩分をコントロールしながら最大限に栄養を摂り入れることが可能です。梅干しと組み合わせる、野菜とともに食べるなど、うなぎは調理や食材の組み合わせを工夫することで一層美味しく、健康的に楽しめます。
自分の体質やライフスタイルに合わせて上手にうなぎを取り入れつつ、栄養価の高い食生活を目指していきましょう。