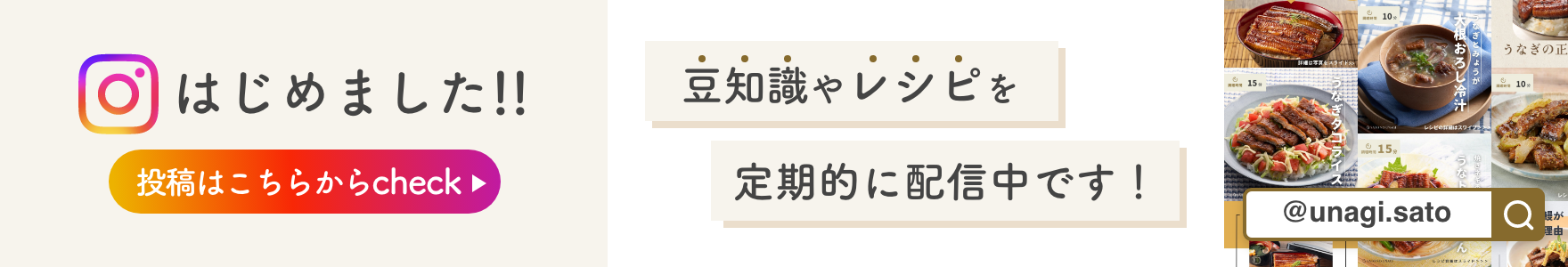うな重の「松竹梅」の違いは?由来やランク付けされる理由について解説

うな重のメニューに「松・竹・梅」というランクがあるのを見たことがある方は多いでしょう。しかし、松竹梅の違いを正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。
実際には、松竹梅の違いは主にうなぎの量によるもので、質や調理方法には大きな差がないことが一般的です。本記事では、うな重の松竹梅の違いやその由来、ランク付けされる理由などについて詳しく解説します。

著者紹介
日本最大のうなぎの産地である鹿児島県から高品質なうなぎをお届けする「さとうの鰻」です。活きの良い鰻のみを厳選して美味しく焼き上げ、全国に発送しております。
今回は、うな重の松竹梅の違いについて解説します。うなぎに関する知識として知っておいて損はないので、ぜひ最後までご覧ください。
松竹梅の由来とは?

「松竹梅」は、もともと中国の文化に由来し、「歳寒三友(さいかんのさんゆう)」と呼ばれる文人画のテーマの一つとして発展しました。
歳寒三友とは、寒さの厳しい冬にも枯れない松と竹、そして寒中に花を咲かせる梅を指します。これらの植物には、日本のような「おめでたい」という意味合いはなく、むしろ厳しい環境に耐える強さや精神の象徴として扱われていました。
この「歳寒三友」が日本に伝わったのは平安時代とされ、時代を経るごとに庶民の間でも親しまれるようになりました。そして江戸時代になると、現在のような「松竹梅」の順序が定着し、縁起の良いものとして認識されるようになりました。
うな重の松竹梅の基本的な違いはうなぎの量!

うな重の「松」「竹」「梅」というランク付けは、基本的にうなぎの量の違いを示しています。多くの店舗では、価格が高い順に「松」「竹」「梅」となっており、使用されるうなぎの質や調理方法は同じで、提供されるうなぎの量が異なるだけです。
また、「並」「上」「特上」といった表記も、基本的にはうなぎの量の違いを示しており、質の違いではないことが一般的です。そのため、うな重の「松」「竹」「梅」や「並」「上」「特上」の違いは、主にうなぎの量によるもので、調理方法や品質に大きな差はないとされています。
うな重とうな丼の違いは器の違い
うなぎ屋さんなどでよく聞く「うな重」と「うな丼」ですが、違いをご存知でしょうか?
うな重とうな丼の違いは簡単で器の違いで、うな重は重箱に盛り付けたもので、うな丼はどんぶりに盛り付けられたものです。聞いただけだと「うな重」の方が高級そうに見えますが、質に違いはありません。
重箱とどんぶり、それぞれの器に込められたこだわりを感じながら食べるのも一つの楽しみでしょう。
うな重が松竹梅でランク分けされる理由

松竹梅が商品のランク付けに使われる理由には、縁起の良さと消費者心理の両方が関係しているとされています。松・竹・梅は、寒さの厳しい冬でも立派に育つことから、縁起の良い言葉としておめでたい場面で使われるようになりました。
また、すし屋ではかつて「特上・上・並」というランク付けをしていましたが、「並」を注文しづらいと感じる客が多かったため、それぞれを「松・竹・梅」に置き換えたといわれています。
この変更により、どのランクも気軽に注文できるようになり、さらに「松竹梅」の美しい響きが、さまざまな業界で広く使われるきっかけになりました。
松竹梅の順番になった理由

「松竹梅」の成り立ちを考えると、竹や梅が最上級であっても不思議ではありません。それにもかかわらず、一般的には松が最上位とされ、竹、梅の順に続くのが主流となっています。その理由には、主に以下の3つの説があるとされています。
中国の仙人に松が振る舞われた説
中国の仙人と呼ばれる人々は、五穀(米・麦・粟・黍・稗)を口にせず、松の実を主食にしていたと伝えられています。仙人を目指す修行者も、五穀を断ち、松の実を食べ続けることで神に近づくと考えられていました。
そのため、松は仙人と深い関係を持つ特別な存在とされてきました。こうした背景から、神聖な存在である仙人をもてなす際には松の実が振る舞われ、それが尊ばれたことにより、「松竹梅」の中で松が最上級とされたという説があります。
縁起物として扱われるようになった時代順説
「松竹梅」は、もともと中国の「歳寒三友」として日本に伝わりましたが、日本国内で縁起物として扱われるようになった時期には違いがあります。
松:平安時代から、不老長寿の象徴として縁起の良いものとされた。冬でも青々とした葉を保つため、長寿の願いが込められた。
竹:室町時代から、大地にしっかり根を張り、まっすぐ成長する姿が子孫繁栄の象徴とされた。
梅:江戸時代から、寒さの厳しい冬に美しく花を咲かせることから、気高さや忍耐の象徴として縁起が良いものとされた。
このように、縁起物として認識されるようになった時期の古い順番で「松・竹・梅」の序列が定着したとする説です。
三々九度の杯の順番説
三々九度は、日本の伝統的な結婚式で行われる儀式の一つで、新郎新婦が同じ杯を交わしながら三度ずつお酒を飲むことで、夫婦の契りを結ぶとされています。
この儀式では、大きさの異なる三つの杯を使用し、それぞれの杯を「松」「竹」「梅」と名付けていたといわれています。この三々九度の杯の順番が、そのまま「松竹梅」のランク付けの由来となったという説もあります。
お店によっては松竹梅の順番が逆のこともある
一般的に「松竹梅」のランクでは松が最上級とされます。しかし、もともと松・竹・梅はどれも縁起の良いものとされており、本来優劣をつけるものではありません。
むしろ、特定の順番を意識させないためにこの組み合わせが用いられたと考えられているため、竹や梅が最上級とされる場合があっても間違いではありません。多くの店舗では松を最上位としています。
しかし、店舗によっては誰かにご馳走する際に格好が付くように、あえて高価格なものを「梅」、手頃な価格のものを「松」と表記するところもあります。そのため、初めて訪れるお店で「松竹梅」の表記がある場合は、思わぬ勘違いを防ぐためにも、事前にメニューの内容をチェックしておくと安心でしょう。
松竹梅に続きのランクはある?

「松竹梅」の続きに特定の言葉が決まっているわけではありません。松竹梅はもともと三つで一つの縁起の良い組み合わせとされており、その成り立ちから考えても、他の言葉が続くことはないとされています。
ただし、結婚披露宴のテーブル名や宴会場の部屋名などでは、松竹梅に続いて「福」や「寿」といったおめでたい言葉が使われることがあります。これは、単に会場内で多くのテーブルを区別するために縁起の良い言葉を便宜的に追加したものであり、本来の「松竹梅」の続きとして決まっているわけではありません。
実際に、結婚披露宴などでは「松竹梅」の後に「福禄寿」「雪月花」「鶴亀」などの言葉が使われることもあり、これらはそれぞれ縁起の良い意味を持つ言葉として知られています。例えば、「福禄寿」は七福神の一人で、「福」は子宝、「禄」は財産、「寿」は健康と長寿を意味します。
このように、松竹梅に続く言葉は場面によって異なりますが、元々の意味としては「松竹梅」で完結していると考えられます。
うな重に最適な絶品通販うなぎをご紹介
ここでは、自宅で本格的なうな重を楽しみたい方や、喜ばれるギフトを探している方におすすめの通販うなぎを厳選してご紹介します。
専門店の職人が丁寧に仕上げたうなぎは、ふっくらとした食感と香ばしい風味が特徴です。電子レンジや湯煎で簡単に温めるだけで、専門店のような美味しさを自宅で堪能できます。うなぎの量や部位に応じたさまざまな商品があるので、自分に合った一品を選んでみてください。
鹿児島県産 うなぎ蒲焼 半身【特大サイズ】 6枚セット
鹿児島県産のうなぎ蒲焼が半身サイズ(約95g)で6枚セットになった、さとうの鰻の定番人気商品です。職人が1尾ずつ丁寧に捌き、白焼きにしたうなぎを、備長炭に近い波長を持つ電気ヒーターとガス火の組み合わせで焼き上げることで、外はカリッと香ばしく、中はふわっとした食感に仕上げています。
2度のタレ漬けと焼きの工程を経て蒲焼に仕上げられたうなぎは、-32度で急速凍結されており、家庭でも専門店のような味わいを楽しめます。ボリュームもたっぷりで、通販で初めてうなぎを購入する方にもおすすめの品質です。お召し上がりの際は、電子レンジか湯煎で温めるだけで簡単に本格的な味わいを堪能できます。
鹿児島産 うなぎ白焼 【中】2尾セット
無頭のうなぎ白焼きが2尾セットになった、さとう鰻の特製白焼きです。外はパリッとした香ばしい食感ながら、噛むたびにほろっとほぐれる柔らかな身が特徴です。1尾あたり143gとボリュームもあり、うなぎ本来の旨味をしっかりと味わえます。
また、シンプルな塩味で楽しめるように、焼塩とゆずこしょうが付属しています。さらに、特製のうなぎタレ(山椒付き)も同梱されているので、タレをつけて蒲焼風に味わうこともできます。シンプルな味わいを楽しみたい方や、お酒のお供にもぴったりな一品です。
鹿児島産 うなぎの蒲焼【大】 4尾セット
1尾あたり約156gの無頭うなぎの長蒲焼が4尾セットになった、贅沢な商品です。ふわふわとした柔らかい食感が特徴で、箸で簡単に切れるほどのやわらかさです。さとうの鰻特製のタレがうなぎの旨味を一層引き立て、脂がのっていながらもしつこくなくあっさりとした味わいに仕上がっています。
白ごはんにのせれば、タレとうなぎの濃厚な旨味が絡み合い、家族全員が満足する一品になります。贅沢なうな重やひつまぶしを自宅で楽しみたい方におすすめです。
鹿児島産 うなぎ蒲焼 きざみうなぎ 10袋セット
手軽にうな丼やアレンジメニューを楽しめる、きざみうなぎの蒲焼10袋セットです。届いたうなぎを温めて白ごはんにのせるだけで、本格的なうな丼が完成します。カットサイズにもこだわり、うなぎの食感や旨みをしっかりと感じられるよう工夫されています。
小さなお子様やご年配の方でも食べやすく、家族みんなで楽しめるのも嬉しいポイントです。さらに、温かいお茶や出汁をかけてうな茶漬けにするのもおすすめです。うなぎの旨味が引き立ち、最後まで美味しく楽しめます。
松竹梅の違い知って自分に合ううな重を選ぼう

うな重の松竹梅は、基本的にうなぎの量で区別され、使用されるうなぎの質や調理方法に大きな差はありません。
松竹梅はもともと縁起の良い言葉として親しまれ、飲食店のランク付けにも広く採用されています。松竹梅の違いを知ることで自分に合ったうな重を選び、より美味しく味わってみてはいかがでしょうか。